改革
- HOME
- 改革
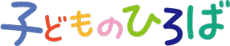

1.「Let’s sing a song ! Sing English songs !」
では、「いじめ」で苦しんでいる子に来てほしい。
歌をうたって気分を明るくしてほしい。
2.「Let’s sing a song ! Sing English Songs !」
では、「不登校」で気分が晴れないお子さんに
来てほしい。自分をどうすればいいか分からない
お子さんに、歌うことで自分の能力に気づいてほしい。
3.「Let’s sing a song ! Sing English songs !」
では、学校で習う英語が分からない。ついていけない。
英語が嫌い。そういうお子さんに来てほしい。英語は、
面白くて楽しい。もっと知りたいとなってほしい。
4.「Let’s sing a song ! Sing English songs ! 」
では、家の手伝い、親の世話、兄弟の世話、習い事を
していない。習い事をするお金がないなど、気分転換
が必要なお子さんに来てほしい。
1.「Let’s sing a song ! Sing English songs !」
では、「いじめ」で苦しんでいる子に来てほしい。
歌をうたって気分を明るくしてほしい。
2.「Let’s sing a song ! Sing English Songs !」
では、「不登校」で気分が晴れないお子さんに
来てほしい。自分をどうすればいいか分からない
お子さんに、歌うことで自分の能力に気づいてほしい。
3.「Let’s sing a song ! Sing English songs !」
では、学校で習う英語が分からない。ついていけない。
英語が嫌い。そういうお子さんに来てほしい。英語は、
面白くて楽しい。もっと知りたいとなってほしい。
4.「Let’s sing a song ! Sing English songs ! 」
では、家の手伝い、親の世話、兄弟の世話、習い事を
していない。習い事をするお金がないなど、気分転換
が必要なお子さんに来てほしい。